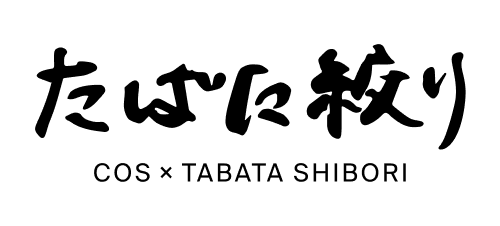

日本の工芸に貢献する絞り職人、
田端和樹氏による
独占コラボレーションが登場。
<picture data-component="APicture" class="a-picture" data-component-id="26dd9fc7-7602-465e-8e6d-146e6967fc63">
g class="a-image" src="/ja-jp/photo/page/2024_shibori/zz-1232776_13-235-1010016-2.jpg" alt="COS LP Stephen Doherty" width="600" height="900">
</picture>
ロングラインシングルブレストブレザー
¥26,000 税込
COS X たばた絞り
<picture data-component="APicture" class="a-picture" data-component-id="37bd5e7f-974d-4083-8598-c8131bd7bda9">
g class="a-image" src="/ja-jp/photo/page/2024_shibori/zz-1232772_13-235-1010016-2.jpg" alt="COS LP Stephen Doherty" width="600" height="900">
</picture>
ストレートレッグストレッチパンツ
¥23,500 税込
COS X たばた絞り
<picture data-component="APicture" class="a-picture" data-component-id="96853ba1-099f-45f9-b757-98111bb7f315">
g class="a-image" src="/ja-jp/photo/page/2024_shibori/zz-1237002_39-204-1010001-2.jpg" alt="COS LP Stephen Doherty" width="600" height="900">
</picture>
オーバーサイズシルクカフタンワンピース
¥31,000 税込
COS X たばた絞り
<picture data-component="APicture" class="a-picture" data-component-id="611882d5-3056-4169-91f0-8746fdebc39f">
g class="a-image" src="/ja-jp/photo/page/2024_shibori/zz-1245350_76-108-1010014-1.jpg" alt="COS LP Stephen Doherty" width="600" height="900">
</picture>
ギャザードAラインマキシワンピース
¥31,000 税込
COS X たばた絞り
<picture data-component="APicture" class="a-picture" data-component-id="a3f0bf51-9b70-48ea-8b5f-53d4ab3036f4">
g class="a-image" src="/ja-jp/photo/page/2024_shibori/zz-1232776_13-235-1010016-2.jpg" alt="COS LP Stephen Doherty" width="600" height="900">
</div>
</picture>
ロングラインシングルブレストブレザー
¥26,000 税込
COS X たばた絞り
<picture data-component="APicture" class="a-picture" data-component-id="3d850035-6880-4e22-b52b-aac1a9db3547">
g class="a-image" src="/ja-jp/photo/page/2024_shibori/zz-1232772_13-235-1010016-2.jpg" alt="COS LP Stephen Doherty" width="600" height="900">
</div>
</picture>
ストレートレッグストレッチパンツ
¥23,500 税込
COS X たばた絞り
<picture data-component="APicture" class="a-picture" data-component-id="c45fb6c1-9c3e-40e7-a722-a5016fd41f16">
g class="a-image" src="/ja-jp/photo/page/2024_shibori/zz-1231644_76-108-1010001-2.jpg" alt="COS LP Stephen Doherty" width="600" height="900">
</div>
</picture>
ハイネックタンクトップ
¥13,000 税込
COS X たばた絞り
<picture data-component="APicture" class="a-picture" data-component-id="335cc532-af37-460c-a7ef-1842c81fc946">
g class="a-image" src="/ja-jp/photo/page/2024_shibori/zz-1244876_77-101-1010001-2.jpg" alt="COS LP Stephen Doherty" width="600" height="900">
</div>
</picture>
半袖リラックスシャツ
¥18,500 税込
COS X たばた絞り
<picture data-component="APicture" class="a-picture" data-component-id="e80f9fa2-ea15-40e7-a390-9783d1b607d2">
g class="a-image" src="/ja-jp/photo/page/2024_shibori/zz-1237002_39-204-1010001-2.jpg" alt="COS LP Stephen Doherty" width="600" height="900">
</div>
</picture>
オーバーサイズシルクカフタンワンピース
¥31,000 税込
COS X たばた絞り
<picture data-component="APicture" class="a-picture" data-component-id="7c247f6a-182b-4eda-9049-fd389fd41aee">
g class="a-image" src="/ja-jp/photo/page/2024_shibori/zz-1245350_76-108-1010014-1.jpg" alt="COS LP Stephen Doherty" width="600" height="900">
</div>
</picture>
ギャザードAラインマキシワンピース
¥31,000 税込
COS X たばた絞り
<picture data-component="APicture" class="a-picture" data-component-id="f2d26a3f-ece8-413e-9732-c6c249d7bf6f">
g class="a-image" src="/ja-jp/photo/page/2024_shibori/zz-1234589_14-129-1010001-2.jpg" alt="COS LP Stephen Doherty" width="600" height="900">
</div>
</picture>
シルクネックスカーフ
¥13,000 税込
COS X たばた絞り
<picture data-component="APicture" class="a-picture" data-component-id="f5a5cce7-468d-4eb1-8449-4db3bbc9df37">
g class="a-image" src="/ja-jp/photo/page/2024_shibori/zz-1231318_13-231-1010001-2.jpg" alt="COS LP Stephen Doherty" width="600" height="900">
</picture>
バミューダゴムショートパンツ
¥16,000 税込
COS X たばた絞り
<picture data-component="APicture" class="a-picture" data-component-id="99d09973-c714-4a7b-8761-76a0467cad66">
g class="a-image" src="/ja-jp/photo/page/2024_shibori/zz-1214024_76-113-1010001-2.jpg" alt="COS LP Stephen Doherty" width="600" height="900">
</picture>
COS ユーティリティートート - キャンバス
¥7,900 税込
COS X たばた絞り
<picture data-component="APicture" class="a-picture" data-component-id="4dff3cab-f7e2-4d72-9381-9cae95860f61">
g class="a-image" src="/ja-jp/photo/page/2024_shibori/zz-1245897_13-231-1010001-2.jpg" alt="COS LP Stephen Doherty" width="600" height="900">
</div>
</picture>
カラードシャツジャケット
¥26,000 税込
COS X たばた絞り
<picture data-component="APicture" class="a-picture" data-component-id="2d1700b6-4d34-4f2f-a15c-f4e58f73be99">
g class="a-image" src="/ja-jp/photo/page/2024_shibori/zz-1231318_13-231-1010001-2.jpg" alt="COS LP Stephen Doherty" width="600" height="900">
</div>
</picture>
バミューダゴムショートパンツ
¥16,000 税込
COS X たばた絞り
<picture data-component="APicture" class="a-picture" data-component-id="cdb4dc54-0f7e-413e-8338-3b0c99aec3a2">
g class="a-image" src="/ja-jp/photo/page/2024_shibori/zz-1214024_76-113-1010001-2.jpg" alt="COS LP Stephen Doherty" width="600" height="900">
</div>
</picture>
COS ユーティリティートート - キャンバス
¥7,900 税込
COS X たばた絞り
<picture data-component="APicture" class="a-picture" data-component-id="73202684-9c46-42d1-a578-4a87c41b287e">
g class="a-image" src="/ja-jp/photo/page/2024_shibori/zz-1231310_76-113-1010001-2.jpg" alt="COS LP Stephen Doherty" width="600" height="900">
</div>
</picture>
キャンプカラー半袖シャツ
¥13,000 税込
COS X たばた絞り







